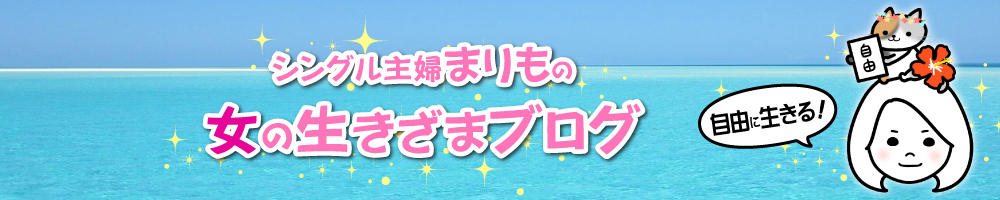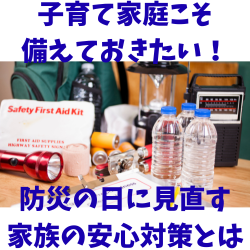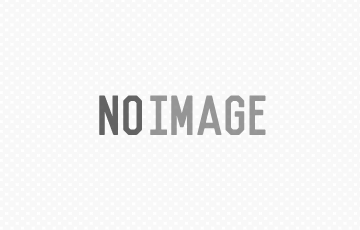9月1日は「防災の日」。特に小さな子どもを育てる家庭にとって、防災対策は“家族の安心”を守る大切な準備です。
非常食や防災リュックだけでなく、赤ちゃん用グッズや子どもが安心できる工夫まで考えておくことが必要です。
本記事では、実際の体験談を交えながら、子育て家庭だからこそ取り入れたい防災の工夫・備え方を分かりやすく解説します。
今年の「防災の日」をきっかけに、ご家庭の準備を一緒に見直してみませんか?
も・く・じ
はじめに(防災の日とは?家族にとっての備えの重要性)

9月1日は「防災の日」。この日は、1923年に発生した関東大震災を教訓として、防災意識を高めることを目的に制定されました。毎年この時期になると、ニュースや学校でも防災について取り上げられることが多くなります。
けれど、日々の育児や家事に追われていると、「うちはまだ準備できてないな…」と気になりながらも、つい後回しになってしまいがちですよね。特に小さな子どもがいる家庭では、大人だけの防災準備とはちがい、“子どもの安全・安心”まで見据えた備えが求められます。
「非常食は?」「避難所に行ったらどうする?」「子どもが不安にならない?」など、不安要素は多くあるものの、きちんと準備すれば、いざというときにも家族全員が冷静に行動できます。
この記事では、子育て中のご家庭に向けて、
- 今からできる防災準備
- 子どものための備え方
- 家族で決めておくべきルールや避難計画
「今年こそ、家族を守る準備をしよう」 と思えるきっかけになるように。忙しいママ・パパでもできる防災対策を、ぜひチェックしてみてください。
子育て家庭に特有の防災対策とは

子どもがいるからこそ必要な“防災目線”とは?
防災グッズや避難計画といった準備は、大人だけの視点では不十分なことが多いです。特に乳幼児や小さな子どもがいる家庭 では、以下のような“子どもならではの事情”をしっかり考慮する必要があります。
1. 子ども用の物資は代用がきかない
大人は我慢できることでも、子どもには厳しいことが多いです。特に必要になるのが以下のようなアイテム
- 粉ミルク・哺乳瓶(液体ミルクだとより便利)
- おむつ・おしりふき
- 子ども用の非常食(アレルギー対応含む)
- 着替えや防寒グッズ(体温調節が苦手なため)
これらは避難所で手に入るとは限らないため、家庭での備蓄が非常に重要 になります。
2. 精神的な不安が大きい
地震や台風などの災害時、子どもは音や揺れに敏感に反応し、恐怖心で泣き出してしまうことも。そんなとき、親がパニックになってしまうと、さらに不安が連鎖します。
事前に防災訓練をしたり、絵本や遊びを通じて「災害ってなに?」を学ばせておくことで、いざというときの子どもの安心感につながります。
3. 移動や避難行動に時間がかかる
乳幼児を抱っこしての避難、歩ける子どもでも長距離移動には限界があります。避難所が遠い場合、途中での休憩ポイントやトイレの場所を事前にチェックしておくと安心です。
また、ベビーカーは使えないことが多いため、抱っこ紐や簡易スリングなどの準備もおすすめ。
このように、子どもがいるからこそ「大人と同じ備え」では不十分 。次のパートでは、実際にどんなグッズを備えておくべきか?を詳しく解説していきます!
今すぐ見直したい!家庭の防災グッズリスト
防災グッズというと、まずは「懐中電灯」や「非常食」といったものを思い浮かべるかもしれませんが、子育て中のご家庭ではさらに必要なアイテムが多くなります。
🎒 防災リュックとグッズの整理例(大人+子ども向け)
ここでは、大人+子ども向けに分けて必要なグッズを整理してご紹介します。
🔷 家族全体で共通して必要なもの
- 飲料水(1人1日3L × 最低3日分) 購入はこちら
- 非常食(レトルト、缶詰、アルファ米、栄養補助食品など) 購入はこちら
- モバイルバッテリー・予備充電器 購入はこちら
- 懐中電灯・ヘッドライト 購入はこちら
- 救急セット(絆創膏、消毒液、常備薬) 購入はこちら
- 携帯トイレ(断水・避難所生活に備える) 購入はこちら
- タオル、ウェットティッシュ 購入はこちら
- マスク、除菌グッズ 購入はこちら
- 現金(小銭含む)、保険証のコピー
🔷 子どもに特化した防災グッズ(年齢別)
👶 乳幼児向け
- おむつ(多めに!) 購入はこちら
- おしりふき 購入はこちら
- 粉ミルク 購入はこちら/液体ミルク購入はこちら/ モバイルミルクウォーマー 購入はこちら
- 離乳食(パウチタイプなど) 購入はこちら
- 抱っこ紐(避難時に必須) 購入はこちら
- 着替え・防寒アイテム(体温調節が苦手なため)購入はこちら
- おしゃぶり、お気に入りのタオルやぬいぐるみ(安心材料)
👧 幼児〜小学生向け
- アレルギー対応のおやつ・食品 購入はこちら
- 簡易トイレ(子ども用に工夫が必要) 購入はこちら
- 小さめマスク、絆創膏
- ヘッドライト(子ども自身で持てるもの)購入はこちら
- 絵本・折り紙・トランプなどの暇つぶしグッズ
- 筆記用具・ノート(避難所での安心材料にも) 購入はこちら
🎒 防災リュックのおすすめポイント
- 大人用・子ども用を分けると避難時に持ちやすい
- 耐水・耐久性のある軽量リュックがおすすめ
- 中身が一目でわかる透明ポーチで整理
- 定期的に中身の賞味期限やサイズをチェックして更新
このリストを基に、防災リュックと中身を揃えておくと、避難時に必要なものをすぐ持ち出せるため、家族全員の安心につながります。
✅ 実際にやってみよう:「1日避難生活シミュレーション」
実際に、家の中で1日だけ電気・水道・ガスを使わない生活をしてみると、「足りないもの」「意外と困ること」がリアルに見えてきます。特に子どもがいると、ちょっとしたことでも大騒ぎになることも。
例えば:
- おむつの枚数が足りなかった
- 怖がって泣いてしまった
- 食べられる非常食がなかった
こうした「気づき」を家族で共有し、少しずつ改善していくことが、真の“備え”につながります。
「怖がらせずに伝える」ことが防災教育の第一歩
災害の話を子どもにすると、「怖がって眠れなくなるのでは?」と心配になる保護者の方も多いと思います。
でも本当に大切なのは、子どもに“正しく知る力”と“行動できる力”を育てること 。
✅ 年齢別の防災の伝え方と工夫
👶 幼児〜未就学児(3〜6歳)
- 遊びや絵本を活用して、「地震が来たら机の下にかくれる」などの動作を楽しく覚えさせる。
- 「ママと一緒にこうするよ」と安心感を持たせながら教える。
- 【おすすめ】防災をテーマにした絵本:「じしんだ!かじだ!」(幼児向け)
👧 小学生以上
- 実際に避難訓練やシミュレーションを一緒に行うことで、自分の身を守る意識を育てる。
- ニュースなどを見ながら「もしこれがうちで起きたらどうする?」と考える時間をつくる。
- 家族で“秘密の合言葉”を決めておくと、緊急時に安心材料になる。
✅ 声かけのコツ:不安に寄り添いつつ、前向きに
災害の話をする際には、以下のような言葉を意識すると、子どもの不安を減らすことができます。
- 「〇〇のときは、こうすれば大丈夫だよ」
- 「一緒にやってみようか」「ママと練習してみようね」
- 「怖かったら言っていいよ。でも準備しておくと安心だね」
子どもにとって何より大切なのは、「自分は守られている」という実感です。
親が落ち着いて話すことで、子どもも落ち着いて行動できるようになります。
家族の安全は“話し合い”から始まる

どんなにグッズを揃えていても、いざというときに「家族がバラバラで行動してしまった」では意味がありません。
特に子育て家庭では、「親と子どもが一緒に避難できないケース」も想定することがとても重要です。
だからこそ、防災の日などをきっかけに、家族で避難計画を話し合うこと が欠かせません。
✅ 家族で決めておくべき5つのこと
1.避難場所と集合場所
- 自宅近くの避難所、勤務先・保育園・学校からの避難先
- 第2・第3の集合場所も決めておくと安心
2.連絡手段の確認
- 災害時は携帯が繋がらないことも多いので、「災害用伝言ダイヤル(171)」やLINEの使い方などを家族で共有
- 離れた親族に「伝言係」になってもらうのも◎
3.役割分担を考える
-
- パパは水の確保、ママは子どものケア、子どもは自分の荷物を持つ…など簡単な担当を話し合っておく
- 小さなお子さんにも「ぬいぐるみを持つ」などの役割で参加意識を持たせる
4.非常時の持ち出しバッグの場所確認
- 「非常袋はどこにあるか?」「誰が持つのか?」を明確に
- 子ども用リュックを用意して、自分の分を背負う練習もしておくと◎
5.ペットがいる場合の避難方法
- ペットの同行避難が可能か、近隣の避難所の情報を事前にチェック
- ペット用防災グッズも忘れずに
✅ 月1回の“防災ミーティング”もおすすめ
普段の生活で忘れがちな防災対策。月に1回でも、「最近地震あったね、うちの準備どうかな?」と家族で確認する時間を作っておくと、備えが“当たり前”の習慣になります。
また、子どもの成長に合わせて必要な物や対応も変わってくるので、定期的な見直しはとても大切です。
子育て家庭の防災は、「できることから」がカギ
ここまで、子育て中の家庭に向けた防災対策についてお伝えしてきました。改めて大事なポイントを振り返ると…
✅ 本記事のまとめ
- 子どもがいるからこそ、特有の備えが必要
- 食事・排泄・安心材料など、大人とは違う観点で準備を
- グッズの備蓄だけでなく、「子どもへの伝え方」も大切
- 年齢に合わせて、怖がらせずに「行動できる力」を育てる
- 家族で話し合う“避難ルール”が生死を分ける
- 集合場所、連絡手段、持ち物の確認は必須
- 定期的に見直しをすることで、本当の安心に近づく
- 子どもの成長、家庭環境の変化に合わせて柔軟に対応
📎 活用できる!防災チェックリスト例(印刷OK)
ご家庭ごとにカスタマイズしやすいよう、基本のチェックリストを作成することをおすすめします。
🧾 チェック項目例:
- 非常食・水は家族人数分そろっている
- おむつやミルク、子ども用食品のストックがある
- 非常持ち出し袋はすぐ持ち出せる場所にある
- 家族で避難ルートや集合場所を共有している
- 災害用伝言ダイヤルなどの連絡方法を確認済み
- 子どもに防災の話をした/防災ごっこをした
最後に

「完璧に備える」のは難しいけれど、“少しずつでも準備すること”が、子どもや家族を守る力になります。
この防災の日をきっかけに、ご家庭でもぜひ「今できること」から始めてみてください。